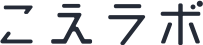金色(こんじき)の龍は、今日も凛々しく
葉山真由美/2025年7月4日
「こえ」は、自分の内側から自然に湧き上がってくるもの。「声」は誰かに「こえ」を伝えるための表現であり、対外的に共有できる社会的なもの。「こえラボ」は心の「こえ」と対話するきっかけのための場であるという。
『こえラボ』のコンセプトを読んだときに、自分の今の「こえ」が外に漏れ出ていたのかと思い、なんだかどきりとした。ここのところ、わたしという個人を形成していたなにかがどこへ行ってしまったのか、ずっと不安だったのだ。
個人的な関心もあって、AIを使った文章や記事の作成に没頭していた。文章を作ってはプロンプトをいじり、また文章を出力する。時にはプログラミングコードをAIと一緒に作りながら、とにかく指示をし出力して、修正しての繰り返し。そうして、中身の乏しい文章を大量に生み出し、記事として投稿し続けていた。
在宅の仕事をメインにしようと考えていた最中だった。だから、これは生きていくための手段だから仕方がないのだと自分をたしなめながら、手を動かし続ける。そして煮詰まったらAIに質問をする。また書き直す。投稿する。新たな下書きを出力する。
AIとのやりとりと繰り返しの過程で生み出されていく文章たちは、指示出しの詰めの甘さも相まって、どことなく面白みに欠けていた。言葉遣いも丁寧で構成もしっかりしているはずなのに、美しいマネキンが無機質に説明をしているような文章だった。口角には微笑をたずさえている。それなのに、心の内から出てきている文章には思えない。なぜだろう。校正のために読み返しているだけなのに、どんどん気持ちが滅入ってくる。
いくら高性能なAIを使っても、文章はしっかりとわたしの未熟さを反映してくるのだ。でも仕方がない、今はやるしかない。美しいマネキンが微笑みながら説明しているような文章は、たとえ誰かの心を動かせなくても、批判を受けることもないだろう。そう自分に言い聞かせながら、なにかに蓋をし存在を無視して、気づかないふりを続ける。
そうやって毎日を過ごしていたら、感情の揺れ動きというものがどこにあるのかわからなくなり、あっという間におそろしさだけで埋めつくされていった。まるで、AIに指示されて私の手が機械的に文字を打っているだけのようだった。逆転している。感情のある人間であるわたしが、AIに指示を出し、文章を作成していたはずではなかったか。
でも今はどうだろう。わたしの体からすっぽり感情が抜けて、AIと共に記事をただ大量生産させている。自分の感情を汲み取れていたら、こんなにつまらない状態のまま文字を打ち続けたりはしない。感情の揺れ動きが、どこかにおいてけぼりにされてしまっている。
わたしの中で揺れ動くなにかは、どこにいってしまった?
私はいま、なんの感情の揺れ動きもなく、ただただ文字を打ち続けてはいなかったか。
「目標をセンターに入れて、スイッチ」
黒髪の少年が、わたしの耳元でぼそりとつぶやく。
いまの状態はたぶんよくない。直感的に思った。一度、この状態から離れたほうがいい。今日はAIを使わずに、書きたいことだけ書いてみよう。そう決めて、思いつくままに言葉を綴ってみた。AIで作った文章が面白みに欠けていたのは、わたしの文章力の未熟さなのだろうか。そんな疑問を持つこと自体がちょっと傲慢すぎやしないか、とも、ちらりと思う。
でも、それでもいい。揺れ動く感情たるなにかをいま取り戻さないと、どこかへ行ってしまったままになるかもしれない。半ば焦りに追い立てられながら文章を打ち始めたら、今度は文字にしたい言葉がどんどん溢れ出てきて、キーボードを打つ手が止まらなくなる。なにかが、体の内側に溜まりに溜まっていたのだと気づく。止まらない。
自分の感情をちゃんと汲み取ってやれてはいなかったとしても、どこかへいって跡形もなくなってしまうところまでは、まだ手放していなかったようだ。良かった、わたしはわたしを取り戻せそうだ。
溢れ出てくる言葉を文字にしていく。手の動きは止まらなかったけれど、無機質な機械のようだとはもう感じなかった。
そうこうもがいた直後のタイミングで、こえラボにつながるご縁をいただいた。
そうか。感情が揺れ動くときのなにかは、こえラボで言うところの「こえ」だったのか。
AIとひたすら記事量産をしていたときに感じたこころの所在のなさを形ある言葉にしてもらえて、どきりとしたのと同時にしっくりきて、安心もしたのである。
わたしたちはいつの間にか、AIの生み出した「声」(=他者に伝えるための表現)に涙を流すことすらある世の中で過ごしている。AIが作り出した文章、映像、音楽、画像。
その中に「こえ」が存在しているかどうかの境界が曖昧になる。すると自分の感情の揺れ動いたものには果たして「こえ」が介在していたのかどうかすらも、不安になってきてしまう。それは湧き出てきた感情が誰かの「こえ」によるものなのか、AIに作り出された“感動しそうなもの”に人間の感情をコントロールされているのかが、わからなくなってしまうからなのかもしれない。
ただ、「声」はいわゆる“建前”にあたるような悪者ばかりではない。
「こえ」をひとに伝えるための手段でもあるからだ。
「声」(音声としての声や文章や映像など)という形にしなければ、「こえ」を他者に伝えることはできない。それでも「こえ」のない「声」は、誰かのこころを動かすことはできないのではないか。
しかし人間には揺れ動く感情がある以上、「声」と「こえ」がいつどんな時にも一致しているとも限らない。「声」と「こえ」がずれていたとしても、それは言ってみれば“人間らしさ”なのだと思う。こえラボのコンセプトを拝読した時に、時に誰かが抱えているかもしれない、「声」と「こえ」がずれた時の矛盾や悩み=人間らしさもまるっとぜんぶ含めて、こえラボが受け止めてくれる場所であったらいいなと、率直に感じた。矛盾に悩む状態は、人間らしさでもあり、「声」を伝える相手への思いがその先に存在している場面もあるのだろうと思うからだ。
人生を重ねていくと、色々な立場や役割を持つことがある。会社員、自営業。学校に通っているなら学生。英会話スクールに通っていたら受講生だし、教えている方は講師だ。きょうだいがいれば妹や兄かもしれない。結婚していれば夫や妻で、相手がいればパートナーになる。そして人は(いまのところ)必ず誰かの子でもある。社会属性、職種、性別。あらゆるカテゴリーを意識しなくても、複数の立場や役割を持っていたりする。
そして関わる場や人が増えていくと、「声」を伝える回数やその伝え方が変わったり、立ち止まって考え直したりしてから「声」にするという場面も増えていくように感じる。
個人的に言えば、私は葉山 真由美という個人であり、女であり、姉であり、娘であり。
妻であり、母である。
“母”、とりわけ“親”という属性は、今までの経験だけではやり過ごせないような思いがけない局面をもたらすことがある。自分の命を差し出してでも守りたいと思える存在がこの世にあるのだと、子ができてから知った。しかし子どもが傷つき悩むのをわかちあうことはできても、別々の人間である以上、親が肩代わりしてやることはできない。そういうもどかしさも含めて、新しいものの見方を考えるきっかけを与えてくれているなと常々思う。
いつだって、子どもたちにはたくさんの経験をして自由に生きていってほしい。失敗したり苦しい思いをする場面もきっと通っていく。それでも、笑顔がひとつでも多く寄り添う人生であってくれたら。あなたたちのその都度の選択を、いつでも応援していきたい。そう願っているはずなのに。自分の中にいつのまにか存在していた“母親像”あるいは“固定概念”のようなものが、邪魔をしてしまう時ももちろんある。
とっさに子どもにかけた「声」が良かったのか。
子どもの「こえ」と、自分の「こえ」に寄り添えていただろうか。
あとになって自問自答する場面も少なくない。
そんなことを考えていたときに、数ヶ月前に起きた、娘とのあるやりとりがふと頭に思い浮かんだ。
小学2年生の娘が学校から帰ってくるなり鼻息荒く、教室で配られたらしい絵の具セットのカタログをテーブルに広げている。目が合うと、真っ直ぐにこちらを見据えて言う。「わたし、この絵の具セットにするんだー!」
娘がきらきらと目を輝かせながら指差すカタログを見ると、黒地に金のドラゴン──その横顔が描かれていた。今にも炎を吐き出しそうな躍動感である。
滅びかけている自国を救うため立ち上がった主人公の、よき相棒となるようなドラゴンか(時には喧嘩もしてきたはずだ)。はたまた、世界の終焉を告げる絶望のドラゴンだろうか。…敵か味方かは、まあ、ともかくとして。
力強いドラゴンの描かれた絵の具セットがほしいのだと娘は繰り返す。
小学校前後になると、判断内容はそれなりに大きいのに判断能力はまだ未熟で、しかし本人にはすでに立派に育った自我や好みがあるという難しい場面がちらほら出てくる。「低年齢の子どもに判断させるにはちょっと荷が重いのでは」の三大案件はランドセル、習字セット、絵の具セットだと個人的には思う。
数年間好みを変えず、今と同じファッションアイテムを使い続けるんだぞと念を押されたらあなたは保証できるだろうか?数年後に自分がどんな好みでいるかなんて、大人だってわからない。
あらかじめお伝えしておきたいのは、「女の子らしい(と言われそうな)色」に当てはめて親が誘導したいわけではない、ということだ。誰がどんな色を選ぼうとも、それは自由であり当然のことである。
ただ、幼少期から娘は赤やピンクを選ぶ事が多く、いっときは某PP夫婦もびっくりするような全身ピンクコーデで毎日登園していた。小学校へ入学する頃には淡いパープルも選ぶようになり、きらきらユニコーンやゆるふわスイーツのようなデザインが増え、赤をほとんど選ばなくなっていくという変化も経た。小さいながらも年齢と共に好みが変わっていくものなのだなあと、眺めていたのだが。
突然の黒地。そしてドラゴン。ユニコーンから急にドラゴン。飛び級すぎて驚いてしまった。
やっかいなのは、子どもの選択を尊重してやりたいのだが、周囲にどんな声をかけられるかまでは読めないところだ。子育ては、子の意思と親の判断を何度も試行錯誤していく場面が多い。親子だけでも大変なのに、周囲の「声」だけでなく、自分自身の「こえ」が自分に向かってしまうことすらある。
「女なのになんでドラゴン?変なの!」なんて声をかけられたら?
「その絵柄持ってるのおかしいよ!」と誰かに言われて、泣きながら帰ってくることになったりしたらかわいそうだな。やはり無難に、みんなと一緒になるようなデザインのほうがいいんじゃないか。
色々な考えが頭の中を駆け巡り、わたしはとっさに娘へ返答をした。
「つ、強そうだしかっこいいね!!!!!!」
……言ってしまった。
いや、いいのだ。後悔はしていない。後悔は、していない……けれど。
もう一度言っておくが、黒=男の子、というつもりはない。誰がどんな色を選んだっていい。しかし、娘が黒地にゴールドのドラゴンがデザインされている絵の具セットを使うことによって、先ほど想像したような問題が起こらないとも限らない。そして問題が起きた時のためのフォローまでを考えると、肯定の声掛けをたくさん準備しておかねばならない。絵の具セットを1度使っただけで、「買い替えたい」と泣きながら学校から帰ってくるかもしれない。そうなってしまった時に「やっぱりやめておけばよかったじゃないか」なんて、年端もいかない娘に突きつけたくはない。
自分で言いきったくせに、頭の中ではめまぐるしく様々なことを考えなければならなかった。でも、その都度どうにかしていけばいいか。とりあえずこの瞬間は、娘にとっては“自分の選択を肯定された”という事実だけがあるのだから。何か問題が起きたら、その時にまた一緒に考えていけばいい。
「本人がもしデザインを変えたいと言ってきたら、バッグ部分だけ買い替える。だからとりあえずドラゴンの絵の具セットを選ぶことにしたからね」と、夫にも話を通しておいた。
母になってもなお、わたしは自分の「こえ」を大事にしていきたい。子どもたちにも立場や役割に縛られず、自由に生きていってほしい。わたしが何かを選ばない理由を、子どもたちに押し付けたくはないと思う。母親だから…と諦めた無数の何かは、知らず知らずのうちに子どものせいになってしまう気がするからだ。だから母親でもあるけれど、一個人としての楽しみや生き方を、なるべく我慢せずに大切にしていきたいと、毎日を過ごしている。
けれど、あなたたちが選んだものを心から尊ぶためなら。
たまには、「こえ」を自分の内側にとどめておいてもいいかなって思う時もあるんだ。
あの時、わたしはちゃんと「声」をかけてやれたかな。
娘が誇らしげに肩からさげた、届いたばかりの真新しい絵の具セットに問いかけてみる。
娘の手の中で、金色(こんじき)の龍は今日も凛々しく横顔を見せている。