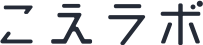そのネットの書き込みは「声」ですか?「こえ」ですか?
坂/2025年4月24日
「声」と「こえ」の共存を研究テーマとして扱う【こえラボ】が新たに発足した。
我々が人や社会に向けて紡ぐ主張――「声」。
そして我々が心の中に抱える形なき本音――「こえ」。
【こえラボ】では、この二面性のある2つの「声/こえ」を取り扱うらしい。
表に出す「声」と、心に抱える「こえ」。
始めに【こえラボ】さんよりこのコンセプトの話を聞いた時、よく漫画や物語などで描かれるシチュエーションに似ていると思った。
「表ではおしとやかな女性が本当はとんでもないヤンキーだった!」とか、
「行きたくねぇ~」とか思いながら口では「楽しみですね!」とか言ってしまう場面である。
「最高ですね!」とか考えながら口では「クソみたいだな!」と言っていて「本音と建前が逆逆!」みたいな総ツッコミを受けるアレである。
と、漫画的なこのシチュエーションをここまで羅列してみてふと「どこかで実際に見たことあるな~」と思って思い当たった。
あるじゃないか。
しかも身近なSNSに。
X(旧Twitter)だ。
Xとは140字でつぶやくことができるSNSである。
Twitterという名前で2007年に発足し爆発的な広がりを見せたこのSNSは、イーロン・マスクに買収されてXという名前に改悪改名され今に至る。
一般人を始め、著名人や団体・会社・レーベルなど幅広い登録者がいて、使用者によってその利用方法も多岐に渡る。
最近ではポストの閲覧数(インプレッション)に応じて広告収益の分配を行うような仕組みも導入され、閲覧数を求めて迷惑投稿を行うインプレゾンビと呼ばれる存在がよく目立つ。
関係ないがこのインプレゾンビをブラウザ上で表示しないようなシステムを導入したところ、友達のポストも消えてしまうのですが彼はゾンビだったのでしょうか。
今度会ったら尋ねようと思う。
とにかくこのXでは複数のアカウントを持つことが可能なため、目的別にアカウントを分けて使っている人が多い。かくいう僕もその一人である。
アカウントの使い分け方には色々なものが存在する。
例えば音楽や小説など異なる趣味の活動報告。
リアル友人と繋がるアカウントと、ネット友人と繋がるアカウント。
そして「表アカ」と「裏アカ」の使い分けだ。
「表アカ」はいわゆる「声」を載せる表アカウントだ。
社会や友人に向けた、自分の意思を表明するアカウント。
簡単に言うと「表向きに取り繕った言葉」を載せるアカウントだ。
「温泉旅行来てるよ~」なんて言いながら美味しい御飯の写真を投稿したり、もはや原型が無くなった自分の加工写真を載せて『究極の映え合戦』が行われるのがこの表アカウントである。
「裏アカ」は表では発信できないようなことを発信する。
知り合いの悪口、著名人の発言への批判、表立って自分の名義では出せない活動。
ブラック企業でやたらと残業させられた愚痴や、ふさふさだった上司が実はカツラだったなどというように、日常では行えないような告発はこの裏アカウントを用いて行われる。
「裏アカ」とは、自分の本心――「こえ」を書くために用いるアカウントだと僕は理解している。
Xでは実に簡単に、直感的に投稿が可能だ。
それ故に人気だが、あまりに投稿のハードルが低いことは問題でもある。
裏アカで投稿しようとしたものを誤って表アカで投稿し、炎上した事件も数限りなく存在する。
関係ないが僕は会社員時代に毎日終電ダッシュした日付をポストしていたら会社の人に見られていたことがある。
SNSの運用には十分気をつけていただきたい。
とまあ、冗談はさておき。
どれが表アカで、どれが裏アカかもわからない。
どれが「声」で、どれが「こえ」なのかもわからない。
そうなればもはやそこに存在するのは混沌だ。
Xという媒体は「声」と「こえ」が混載された闇鍋みたいなものなのである。
ここまでXについて書いたものの、この「声」と「こえ」の混載は、蓋を開けてみると実はネットの至る所で溢れている現象でもある。
しかも、最近に限ったお話ではない。
僕は京都のとある田舎町の出身であるが、実は通っていた中学に『裏サイト』なるものが存在した。
今からもう20年以上も前のことだ。20年以上も前なの……?(36歳)
当時はまだ携帯電話が普及したばかりだった。
今のようなLINEグループは当然のように無く、情報もまともに回らないような時代だった。
そんな時代に何故そんなサイトに行き当たったのかは今となっては覚えていない。
友達から口コミで教えてもらったのかもしれない。
ネットの情報が口コミで広がるというよくわからない現象が起こっていたところにネット黎明期クオリティを感じる。
さて、この『裏サイト』では5ちゃんねるのようなスレッドが立ち、テーマ別に雑談したり学校イベントの感想が書かれたりしていた。
『裏サイト』というと、ついつい教師や特定の生徒の悪口などが溢れた殺伐としたものを想像しがちだと思う。
だが意外とそうした誹謗中傷の類の書き込みは少なく、いわゆるクソスレが乱立していた。
【◯◯中集合!】お前らの今の気持ちを言え
1 迷える子羊:授業面倒くせー
2 ろくでなし男:台風で学校休みにしろ
3 さつま揚げ大好き:早弁したら怒られたんだけど何で?
4 迷える子羊:逆に何で怒られないと思った?
※名前はいずれも仮のものです。
などというように、クソスレで会話されている内容は本当に取るに足らないものばかりだ。
そのため、サイト自体は割と平和な運用がされていたような気がする。
『裏サイト』のくせに微妙にお行儀が良かったのも、ネット慣れしてないネット黎明期ならではと言えるだろう。
そんな平和な裏サイトにある日、荒らしが現れた。
120 A:ここか、陰キャ共の巣窟は(笑)
Aという人物が突然現れ、平和だった裏サイトに一石を投じたのだ。
この書き込みにムカついた僕は田中という偽名でこう書いた。
121 田中:何やお前は、死ねば良い
120 A:あ?誰やお前。名前書けよ。殺すから
122 田中:書くわけ無いやろ。アホか
123 A:名前も書けへんくせに喧嘩売ってんなよ雑魚
124 ろくでなし男:田中はインポ
125 さつま揚げ大好き:田中はヘタレ
126 迷える子羊:田中はクソ
※田中以外の名前はいずれも仮のものです。
Aに反応した田中が最終的にボコボコに叩かれる流れになったのですが、何で僕は叩かれたのでしょうか。
36歳になった今も答えを探している。
とまぁこのような形で、裏サイトではほぼ全員が匿名で書き込みをしていた。
そのため、このサイトでは表に向けられた「声」ではなく、自分の本心とも言える「こえ」が溢れていたと思う。
ちなみにこの裏サイトは卒業してから半年後くらいに消えていた。
もちろんこれはただの一例だが、どこぞの田舎の中学生ですら20年以上も前からそうしたネットの使い方をしていたのだ。
ネット全体で見れば似たような使い方をしている人は昔から無数にいたと言えるだろう。
つまり、ネットでは黎明期から「声」と「こえ」の混載は始まっていたとも言える。
人が誰かに向けて出すのが「声」で。
『何か』になる前のむき出しの感情そのものが「こえ」だとするならば。
僕達が今日ネット上で投稿したものは「声」だろうか「こえ」だろうか。
そして僕達は果たしてそれを定義づけて使い分けることができているのだろうか。
社会で生きる人間の大半は言葉にオブラートを被せる。
例えば自分が友人の書いた小説や漫画を読むことになったとして、本人を眼の前にして感想を言う場合、何かしら言葉を取り繕うだろう。
友人に対して意見を言うにしても、相手を気遣った言葉選びをするはずだ。
なぜなら「忌憚ない意見を」と言われて忌憚ない意見を本当に言うと嫌われるからだ。
人間とは複雑怪奇な生き物で不可解で理不尽である。
言葉をオブラートで包むとは、社会的価値を落とさないための自衛手段なのだ。
一方でネット上の書き込みはどうかと言うと、オブラートに包まれていない本音が記されていることが多い。
なぜならネットでは高い匿名性が利用できるからだ。
かつて田中だった僕がリアルファイトしようとするAから匿名性を利用してドロンしたように、匿名性を利用すれば実生活で問題が起こりそうな粗暴な言葉遣いをしても大きなダメージは中々受けない。
最近ではあまりに悪質な人間には、多額の費用をかけて開示請求なども行われている。
ネットでは「こえ」が限りなく原石に近い形で「声」にされている。
SNSにブログ、レビューサイトやイラストに動画。
昨今、表現の舞台となるプラットフォームはどんどん拡大し、自分だけの居場所を作ることは容易になった。
そうした最新鋭の技術を使うのは人間だ。
技術は間違えずとも、人間は実に簡単に間違いを犯す。
中学時代の僕がそうであったように、炎上の根源となるのは人間側の倫理観の問題である。
現在の最新鋭の技術を使えば、僕らは心の中の「こえ」を、多様な形で「声」にできる。
でも、「こえ」を「声」にするための便利なサービスや技術は使い方一つで表情を変えてしまう。
優れた技術は善意や悪意の双方を簡単に「声」にできてしまうからだ。
今日投稿したそのポストや書き込みは果たして「声」なのか「こえ」なのか。
ネットに投稿した「こえ」は、本当に正しく「声」にできているのか。
大切なのは、その疑問を常に胸に抱えておくことだ。
そうすれば、誤った目的で新たなサービスや技術を利用するリスクは減らせる。
インターネットと――ないしこれからの時代に生まれるであろう新たな技術と付き合っていくために、心に刻んでおきたい。