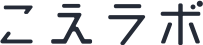悲しみとは何か。こころの哲学から考える──『悲しい曲の何が悲しいのか』を読む。
中田健太郎/2025年8月18日
他人のこえと、内なるこえ。生きていると、相反するたくさんの声を聞くことになる。そして、文章にすれば同じ内容でも、その聞こえ方は人によって全く違うものになってしまうことはよくあることだ。では、僕たちは言葉を声にのせてやり取りするときに、感情を内側に留めたままでしか生きていくことができないのだろうか。
今回紹介する『悲しい曲の何が悲しいのか』という本は、このような問いに客観的に答えようとする。感情、特に他人の感情について客観的に解釈しようとすることは暴力的だと思うものだ。しかし、時に分かり合えないのではないかとさえ思う個人的な感情について、少し引いた視点で自分を見直すことで落ち着くこともある。
日常の生活の中で、たくさんの出来事と遭遇する。その度に、私たちの心は動かされている。緊張感のあるテレビのニュース、意外と美味しくできた料理、好きなバンドの新しいアルバム。選挙カーについては、聞こえた瞬間にはうるさいなと思うけれど、意義を考えるとそうとも言えない、という感情。僕たちは気付かぬうちに、身の回りにあるものの良し悪しを判断しながら生活している(もしくは、疲れすぎていると心を動かされることさえ難しいかもしれないが)。
その判断は、それぞれの価値観に基づいていて、互いにその良し悪しを論じることができないような気がする。好みや趣味というのは人それぞれだから、身の回りにあるものの良さに正しさなんてない。とはいえ価値観というのは、国を違えば全く違うものになる。海外に行くとあまりに常識が違って驚くことがある。翻って考えると、僕たちは自分の身の回りに存在する、比較的よく似た価値観の中で、とても細かい違いを気にしているようだ。
『悲しい曲の何が悲しいのか』という本は、タイトル通り、音楽を聴いた時に私たちが抱く情動がどのようなメカニズムで生じているかを考察している。驚くべきことに、著者は、「美的判断は客観的なものである」という結論を下している。あれ、曲を聞いた時に感じるものって人それぞれ、つまり主観的な気がするけどなぁ。しかしながら同時に、「いや、流石にその解釈は無理があるのではないか」と思うこともある。そもそも、そのように、作品の良さを語り合うときに度々議論が起こるということは、美的判断についての正解らしきものがあると想定できるからと考えることができるのだ。
曲を聞いた時に抱く情動は、例えば「楽しさ」や「怒り」、「悲しみ」といったものだ。これらの情動は、人間が生物であるから存在している。本書においては、「怒り」は「自分が価値を置いているものの侵害」によって、また「悲しみ」は「自分にとって重大な喪失」によって生じるという。
『ある場面でどの情動が生じるかは、どう言ったものに価値を置いているかに応じて変わってくるのである。〔……〕この点を理解するうえで重要なのは、価値は主体と状況の関係によって決まるものだということである。〔……〕生物学的に決定されている価値だけでなく、社会的に決定されている価値も、客観的(ないし間主観的)なものであり、個人の考え方でどうにかなるものではないのである。〔……〕情動はすべて個人の価値に根ざした反応だという考えは間違っているのである。』(p.72-73)
言われてみれば、私たちが日常において他人とすれ違っていると思う時は、自分と他人が大事に思っていることが違うことが原因であることが多い。それはつまり、情動という現象は必ずしも個人の内側で完結するものでもないし、かといって、完全に社会的に決定されるわけでもないということである。ある社会の中で、大切なものが完璧に共有されていたとしたら、怒りや悲しみという情動が発生することはない。そのことを、間主観的と呼んでいる。
そしてこのことは、「悲しい曲の何が悲しいのか」という問いに答えるとき、個別具体的な作品の批評は必ずしも必要ではないということを意味している。もちろん、ある曲のイメージについて話す時、その曲についての背景知識などは影響を与えるはずだ。美的経験というのは、必ずしも一つの感覚に基づいたものではない。音楽だったら聴覚が中心となって、レコードが回っている様子や目の前でギターを弾く姿、はたまたスマホの中のジャケットの写真を見る視覚と、それからその作品に関する知識が相俟って、一つの認識を構成している。
一つの対象に対して複数の知覚や知識があることで、独特な情動が頭の中に浮かんでくる。あるデザイナーの知人は、「良い文章を読んだ時の感覚と、良いデザインが出来上がった時の感覚と、山に登った時の感覚が、同じように感じられる」と話してくれた。これはまさに、複数の経験が重なった時に、新しい感覚を生み出すことの恒例だろう。僕は山を登る趣味はないから、「登山は、山に昇った時がいいんだよ」と言われてもその良さはピンとこない。しかしその裏側には、登山の準備をし、道中でさまざまな発見をし、半ば朦朧とした意識の中で山頂からの風景を見る、という一貫した経験の流れがあるはず。それを頭の中で再構成した結果として、その時抱いた情動は、一つも欠かしてはならない経験の積み上げたてっぺんに存在するのである。同じように、文章も積み上げたピースがあるからこそ良いと思うし、出来上がったデザインも絶妙な配置のバランスが肝要である。
このように、さまざまな知覚や経験が束になったものを「ゲシュタルト知覚」という。私たちが使っている文字はいくつかの部分に分かれているが、それらをひとまとめに認識することで、部分の総和以上の意味を感じ取ることができる。これができなくなった時、ゲシュタルトは崩壊する。
ゲシュタルト知覚は個別的なものであるものの、その結果として抱く情動は単純であれ複雑であれ、抱く条件を想定できるものなので、悲しい曲の条件はある程度想定することができる。とはいえ問題は残っていて、それは曲をきいて悲しいとき、「自分にとって重大な喪失」は起きていないということである。実際に起きてはいないことをなぜ悲しむことができるのだろうか。また、曲自体が悲しみという感情を持つことはない。その上、作曲者が悲しかろうが哀しくなかろうが、聞き手はその曲を「悲しい」ということができる。私たちが「悲しい曲」という時、その悲しさは「私」にも「作曲者」にも「曲」にも、どこにも実在していない。情動は、私と社会とその記憶の総体として存在しているのである。
本書の本当の目的は、美学と哲学に、心理学や神経科学といった認知科学を導入することにあった。今回の書評では取り扱わなかったが、このような分野に関心のある方はぜひお手に取ってみてください。また、悲しみという一見取り扱いづらい感情(実際に悲しい人に悲しさとは何かを論じるのは野暮だと思う)は、必ずしも個人の中にとどまるものではないということは強調しておきたい。それは大切なものの喪失のことであり、私たちが何を大事にしているのか、そしてそれに気づいたときに私と外界を繋ぎ止めているものを知ることができるのだから。