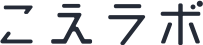歴史という経験
西平将紀/2025年4月24日
旧暦の12月8日、沖縄では1年で最も寒くなる季節「ムーチービーサ(鬼餅寒)」が到来し、今年もまた旧暦通り、とても寒い日だった。しんと静まりかえった朝の空気が、ずっと遠くの小鳥がさえずるのを教えてくれる。そんなピンと張り詰めた朝が、沖縄にも数日訪れる。
そんな朝に私は車を運転していて、少し空気がこもってきたところに外の空気を入れたい気持ちになった。そんな時に「運転席側の窓をあけるか、あるいは助手席側の窓をあけるか」という命題が一時的に私をつかんだので、少し考えてみることにした。
運転席側をあければ直に冷たい風が当たってしまうし、かといって助手席側をあければ冷たい風が渦を巻くように車内に入ってきて、それはまた肌寒い思いをするだろうと思った。ただ私は空気を入れ替えたいので、どちらか一方を選択しなければいけないのだが、どちらも一長一短で、けっきょく肌寒い思いをして目的を達成することに変わりはなかった。そういうわけで開き直った私は、両方の窓を少し開けて、そんな命題も一緒にスルスルと外へと追い出したのだった。
さて、空気も入れ替わった車内で、ふと私はこんなことを考えた。
「こういう個人的な考えは、私がさっき感じた一回きりのことで、特段誰に聞かせるものではないし、誰に聞かせたとて、何らか意味のあるなにかを取り出せるものでもない。でも、これはこれとして、ただの現象として私という人間の輪郭をつくっていくのかもしれない。そういう現象の積み重ねが私を形づくっていくのであれば、私のこの考えや現象が、私をこえていくことで、新しいコミュニケーションが生まれたり、私の人間の位置というか、限定性というか、時代性のようなものが残るのかもしれない」
ドライブ中はこんな風にいろいろなことを考える。そして、そのどれもが考えから出て行かず、声にならないまま窓の隙間からスルスルと抜けていくのである。声にするには、それが入る枠が必要で、その枠がないところにはあまり踏ん張りがきかないのだ。社会はきっと、みんなが思っている以上に枠が必要で、枠のないところに生まれた思念はちょっとした風で吹き飛んでしまう。私が速く移動する存在なら、なおのこと速く飛び去ってしまう。
私たちが生きる今という瞬間が速く過ぎ去ってしまっているか、そんなことは私にはわからない。けれども、高速道路で走る隣の車がゆっくり動いて見えるように、私たちが今この瞬間を、今この視点から見たままでは、本当のことが見えにくいのかもしれない。今生きる私たちを、過去や未来の人間たちはどう眺めるだろうか。
ーーーーーーーーーーーーーー
哲学者の千葉雅也さんが『「失われた時を求めて」を求めて』(中央公論.jp)と題した論考で、こんなことを書いていた。
「強く言えば、人間が個人ではなくなる方向に向かっている。個人的であること自体が悪だというかたちで、伝統的な悪の問題が今日再発見されている。公共的存在として生きるのが善だというのは、楽園を目指すことである。だが今改めて、悪の権利を言うべきではないのか。必然的になされるべきことだけが行われるのではなく、時宜に合わない出来事が起きるのが時間のリズムである。個人たちの時間。それがなくなれば、世界は永遠である。時間がない。歴史がない。世界は全体として歴史がなくなる方向に向かっているのではないか。・・・(中略)・・・個人的実感として言えるのは、一方向的に進んでいくものとしての時間が、その実感が、ある時期から失われたということだ。」
私がドライブ中にたまに考え込んでしまうようなものは、今回こうして書かれる先があって、それを何かの文脈で読む人がいて、はじめて書かれるに至った。こういう機会も大げさにいえば、ある歴史のなかにある。書いたものが、なかば約束された形で読まれると分かるから、書き手に書く意欲がわき、何もなかったところに言葉が紡がれる。そして言葉として認識される時、はじめて言葉以前の存在が明るみになる。
よく考えてみれば、私たちの日常のさまざまな考えも、それが文字や言葉になる場があるから、はじめて声になるのではないか。家族の団らん、職場の同僚、親しい友人、ご近所さん、そういう人たちとの間で交わされる何気ない会話も、それが会話の場として機能しているからこそ、なにか言いたいことが浮かんでくるのではないか。とても当たり前の話をしているような気もするが、意外にも私たちは日常そんなふうに考えることは少ない。「なにか言いたいことがある」「なにか伝えたいことがある」そういうふうにして考えがちだが、もし家族と離れて暮らしていて、それも毎日1人で孤独に過ごしているとしたら、私から出て行く思念はどれだけ少ないものになるだろう。
千葉さんが書いたのは、これまでの文明や数々の歴史が生み出してきた、決して効率的とは言えない時代遅れになった産物が、意外にも「日常」を形作っていたのかもしれない、ということではないか。私たちが今生きているということが、良くも悪くも一度きりだと思えるのは、たった一度の今を印象づける「なにか」がうまく機能しているからである。これを千葉さんは「出来事の出来事性」とよんでいるが、今はいろんなことが避けられるし、何回でもやり直せることが増えたせいで、一回の大切さや出来事の重みがうまく感じられない。でも昔は(学生時代は)出来事の一回性が強かった気もする。それは学校の場が出来事性を印象づける装置になっていたからと考えることもできるし、社会ではそういう半ば強制的なものがほとんどないからだろう。学生時代のような「一緒になにかをした」という記憶は、これからはそう多く作ることができず、歴史や伝統というようなものは意味を失っていくのかもしれない。
こうした現象は、学校や職場、地域が「多様性」などという言葉に耳を傾け過ぎて、結果ないがしろにしてきたことに端を発してような気がしている。多様性とは、つまり選択肢があるということである。どんな判断も個人に委ねられていて、その意志を咎めるのなら、それは法によって裁かれるのであり、職場の同僚や隣人ではない。さまざまな機関や組織も強くは言えない。なにかを言う前に、その相手はどこかへと消えてしまう。強く言うために踏ん張ろうとしても、そこに誰も居ないのであれば、踏ん張りがきくはずもない。そんなふうにして言えないことが増え、言わなかったことが増え、あったものがなくなり、あるはずのものがないのである。
伝統は煩わしい、歴史はただの出来事。そういうムードが人々を支配していて、誰も自ら進んで伝統や歴史を守りたいとは思わないだろう。しかし、日々生きるなかで、私たちはなにかを考えずには居られない。それをすべて一人で抱え込めるほど、強い存在でもない。そういう時に、私たちは文字や言葉を使って誰かに声を届けたいと思う。でもそこに、今日まで続いてきたさまざまものがなかったら、どう伝えればよいのだろうか。なにを表せばよいのだろうか。私はそこに一度きりを印象づけるなにかがあったらいいなと思う。