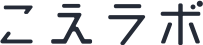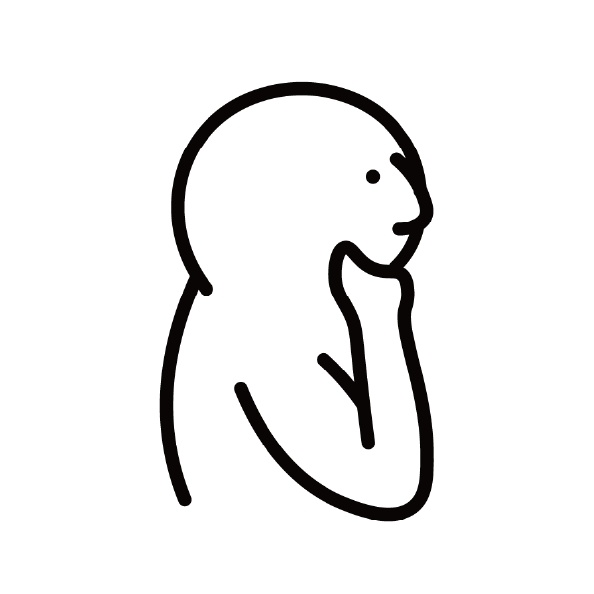書籍紹介『うしろめたさの人類学』
こえラボ編集部/2025年9月19日
私たちはいま、ある程度の便利さがある日本社会の中で暮らしています。それぞれが働いて得た報酬で、あらゆるものを手に入れることができる。法整備が機能している国の中で、暮らしも経済活動も自由に許されているはずなのに、どことなく窮屈なのはなぜなのでしょうか。
こえラボ編集部の葉山です。
本書は文化人類学を専門とする著者・松村圭一郎さんが、学生時代から度々訪れているというエチオピアでのフィールドワークを通して、日本社会でなぜか感じてしまう「生きづらさ」に新たな視点をもたらしてくれる本です。
本書では、社会とはそもそもどう構築されているのかを、市場の仕組みから国家の機能についてまで、著者のエチオピアでの経験も交えながら丁寧に説明してくれます。さらに人と人をつなぐ贈与の概念にも注目し、私たちが日々当然だと疑わない、日本社会の枠組みを見直す(再構築する)きっかけを提示してくれます。
社会のあたりまえからはみ出したものを、ないものとして見て見ぬふりをすることは簡単です。他者の行動や言葉を自己責任として当事者だけに押し付けることも、あるいは国や政治のせいにして無視を決め込むことも、私たちは容易にしてしまう。それは、どこか「生きづらい」と感じている社会を、ゆるやかに肯定し続ける行動でもあります。
はみ出したものを私たちが見て見ぬふりをするのは、他者の直接的な言動=“声”だけに耳を傾けている方が楽だからなのでしょう。他者の心の中に湧き起こる言葉=“こえ”を聞けば、私たちはその人の思いを知り、つながりを引き受けることになります。それには苦しみも面倒さも伴うから、私たちは受け止めるものを“声”だけに留め、「他者と深く交わらない傍観者」になることを、無意識のうちに選択してしまいがちなように思います。
しかし、目の前にある格差にあえて目を向けると、ほのかな「うしろめたさ」が生まれます。その「うしろめたさ」を公平にしようとする感覚こそに、倫理性が宿るのだと松村さんは語ります。本書に登場するエチオピアを見ていると、誰もが当事者となり他者とつながることに、私たちもあえて目を向けて生きていけたなら、分断された仕組みの中で社会を構成する私たちの関係性も、変わっていくのではないかと感じることができます。その変化は、ひとつひとつは小さくても、私たちが生きる世界の「生きづらさ」をやわらげていく行動ではないでしょうか。
【こえラボとは】
心の“こえ”と対話するきっかけとなるような、さまざまな作品を発信しています。

【寄稿記事の募集】
こえラボでは、心の“こえ”をテーマにした作品を募集をしています。あなたの“こえ”を聞かせていただけますと幸いです。