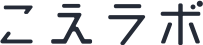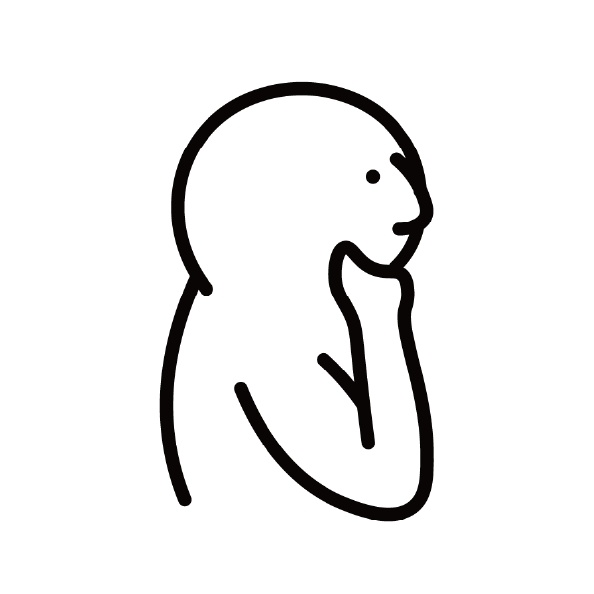『小名浜ピープルズ』刊行記念トークイベントレポート
こえラボ編集部/2025年10月16日
『小名浜ピープルズ』は福岡県いわき市小名浜出身・在住の小松理虔(こまつ・りけん)さんが地元の人たちとの対話を通して、東日本大震災と福島第一原発の事故後10年を人々がどう暮らしてきたのかを綴ったエッセイです。本書の刊行を記念し、横浜市にある本屋・生活綴方で7月17日に開催されたトークイベントを、こえラボ編集部の葉山がレポートします。
今回は『小名浜ピープルズ』著者の小松理虔さんと、とある社会福祉法人で働く職員の方々の言葉を通し「ただそこにいるということを認め合う」あたたかい眼差しを描いた、『らせんの日々』著者の安達茉莉子(あだち・まりこ)さんが登壇しました。
場所について書くということ
小名浜で旧知の人たちとの対話を綴った小松理虔さんの『小名浜ピープルズ』と、京都府城陽市にある社会福祉法人・南山城学園で働く職員の方々の思いを綴った安達茉莉子さんの『らせんの日々』は全く別のテーマによる著作のように見えますが、「人々との対話と著者の感情の揺れ動きを通し、場所について書く」という共鳴する部分があります。
トークイベントでは、安達さんから「相手の言葉だけではなくあえて自分も文章の中にはさみこむことによって、相手の語りがわかりやすくなる瞬間がある」というお話が登場しました。「色々なことに対して心が揺れ動いた自分もそこに置くことで、関係性や距離感も通して相手をより浮き立たせることができると考えた。なぜ自分が驚いたかは自分のことやそれまでの歴史も書かないとわからない(安達さん) 」「知人の変化を知っているのも自分だから、時間や関係性の変化を書いたほうがむしろ謙虚な気がして入れた。自分がピープルズと読者の補助線に入ることができる(小松さん) 」と、文章の中にあえて自分たちの感情の揺れ動きも綴ったのだと語ります。これまでは評論の体をとった書籍も多かった小松さんですが、本書は「小名浜に暮らす人々を書くにあたり地元の人間として感じたこと、過去からの関係性も書いた。結果、今回が初のエッセイかもしれない」と仰っていました。小松さんは「どこかの土地で暮らすということは、その土地も背負うということ」と続けます。
小名浜の歴史を含めて土地を知り、対話を通し揺れ動く小松さんの感情とさらなる問いを辿っていくと、私たち読者の立ち位置もピープルズに引き寄せられ、よりくっきりと小名浜を見ることができるように思います。
線をどうあつかうのか
小名浜は放射能による避難区域ではなかったため「自身の立ち位置はとても中途半端だった」と語る小松さんは、「より大きな被害を受けた方を前にするとなぜか自分の当事者性を下げ、震災について語っていいのか迷ってしまう。当事者か当事者以外かの二択ではなく『共事者』という括りを使いたい」と話します。小松さんの思いが象徴的な、2023年に開催された「常磐線舞台芸術祭」に寄せたステイトメント(イベントの目指すものや導入のメッセージ)がトークイベントの中で読み上げられました。『小名浜ピープルズ』本文にも登場します(146頁)。
「手繰り寄せる、線を」
わたしたちは線を引く。
わたしとあなた、自国と他国、
北と南、東と西。
いつの時代も、どの土地でも、
わたしたちは線を引き、
自分たちが何者であるかを知ろうとしてきた。
そしてまた、わたしたちを「圏内/圏外」というように切り分け、
「来てはいけない土地」を作りもした。
けれど、内と外をつなぐのも線だ。
道によって点と点は線となり
ヒトとモノはめぐる。
共感や情という線は、
その姿形は見えなくとも、
わたしとあなたを隔てていたもう一本の線を溶かし、
あるいは超え、くぐり抜けてゆく。
そのことを、わたしたちは大きな災害を通じて感じ取った。
線は、わたしとあなたをつなぐだろうか。
それとも、分かち断っただろうか。
わたしとあなたの線。演者と観客の線。
生者と死者の線。圏内と圏外の線。
線は今、どこにあるのか。
どこに引かれていたのか。
考え、そして問いたい。
だから、わたしたちは、手繰り寄せる。
その線を。
相手の線を手繰り寄せ、躊躇なくつなげてくれる小名浜の人たち。そして同様に、小松さん自身も人と関わり続け、文筆の傍ら、小名浜でオルタナティブスペースUDOK.の運営を続けられています。
関係性と距離
「愛とは気づくこと、知ること、そのままを認められること」。小松さんと安達さんはイベントの中でそうまとめていらっしゃいました。相手との距離が近いからこそ、『小名浜ピープルズ』に登場する方たちはみな魅力的で、その関係性は愛おしくも感じます。
こえラボでは、私たちは2種類の声を持っている、と考えています。ひとつは、人に伝え共有するために発する“声”。もうひとつは、心の内に響く“こえ”です。『小名浜ピープルズ』には様々な感情が描かれ、まさにありのままの“こえ”が綴られています。
私たちが誰かの“こえ”に耳を傾け、揺れ動く自分の“こえ”にも耳を澄ませ、新たに湧き上がる問いを受け止めるとき、苦しくなることもきっとあるでしょう。聞こえてくる“こえ”は、きれいなものばかりではないからです。それでも、ピープルズや小松さん、安達さんのように“こえ”に向き合うことを諦めずにいれば、私たちも周りにいる人と線を手繰り寄せあうことができるのではないか。本トークイベントは、私たちが“こえ”に向き合い続けていこうとするならば、そこに伴う苦しみもありのまま肯定し、背中にそっと手を添えてくれるような時間でした。
トークイベント概要
【こえラボとは】
心の“こえ”と対話するきっかけとなるような、さまざまな作品を発信しています。

【寄稿記事の募集】
こえラボでは、心の“こえ”をテーマにした作品を募集をしています。あなたの“こえ”を聞かせていただけますと幸いです。