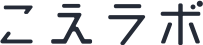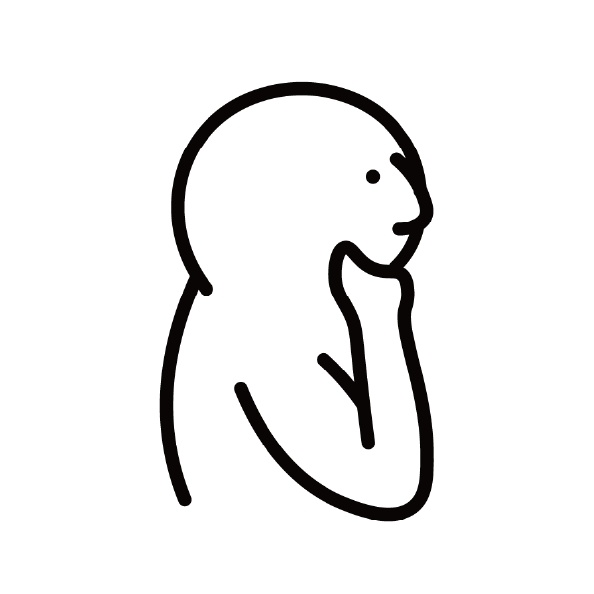書籍紹介『赤を見る 感覚の進化と意識の存在理由』
こえラボ編集部/2025年7月17日
心のうちに響く“こえ”とは、そもそも何なのか?
私たちが“こえ”を“こえ”だと認識し、輪郭を形取るまでに、どういった過程を経ているのか。
“こえ”をさらに分解し、その先の“声”を見つめていくヒントになるかもしれないと感じた書籍をご紹介します。
こえラボ編集部の葉山です。
本書は、著者のニコラス・ハンフリーが2004年にハーバード大学で行った招聘講演の内容を書籍化したものです。講義冒頭でスクリーンに赤い光を当て、「赤いスクリーンを眺めるあなたたちの心の中では何が起きているのか?」と語りかけた著者が、知覚・感覚・意識の違いとその意義に至るまでを、紐解きやすい言葉選びとシンプルな図解を用いて、丁寧に導いてくれます。
赤い光を「知覚」するという科学から、主観的に感じて内面で形取る「感覚」という哲学、『赤を見る』という経験から付加価値や意味を見出す「意識」、そしてその先にいる他者を見据えた社会性へとつながっていく芸術表現にまで、本書の内容は様々な分野に及びます。それは一見、雑多にも見えるけれど、むしろ人間がもつ複雑さからすれば、きっと自然なことなのではないかと思います。
ニコラス・ハンフリーは、「感覚」と「意識」は人間という存在の社会性・共感性・倫理性の源泉であり、人間が人間たる所以であると説明しています。同時に、私たちが何かを感じるとき、感覚として捉えることはすなわち、形取って私自身に認識させること=“こえ”として捉える行為だと位置づけています。
ただ、この“こえ”は他者と共有することができません。私の感覚と、あなたの感覚が全く同じだとは限らないからです。しかし、その感じ方のズレこそが、その先にある「他者の存在」をよりはっきりと感じさせてもくれます。もし孤独を感じたとしても、他者性と社会性がなければ、そもそも孤独という感覚が起こり得ないからです。
恐れずに言えば、このズレはむしろ私たちが人間であることの魅力でもあり、他者と築き上げた社会の中で生活していることの価値と循環でもあります。
この前提は、時に苦しさや面倒さも感じるかもしれない、“こえ”に向き合うための歩みを後押ししてくれるような気がします。
この“声”が、あなたの“こえ”を知るきっかけになるような、本との出会いになれたら嬉しいです。
【こえラボとは】
心の“こえ”と対話するきっかけとなるような、さまざまな作品を発信しています。

【寄稿記事の募集】
こえラボでは、心の“こえ”をテーマにした作品を募集をしています。あなたの“こえ”を聞かせていただけますと幸いです。